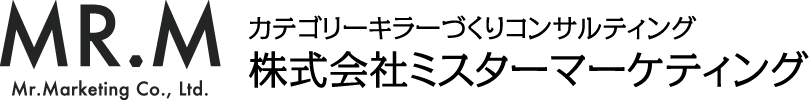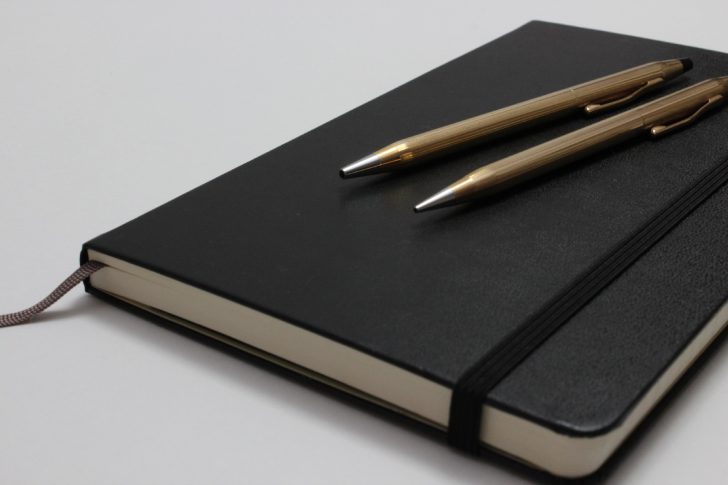第129話 今の事業を伸ばしながら、新規開拓ができる組織をつくる! もし今の売上がなくなったら——その問いへの備え

「先生、うちの会社は今は順調ですが、主要顧客に頼りすぎている気がします。将来的に何かあったときのことを考えると、いまのうちに新しいお客様を開拓する体制をつくりたいんです。」
先日ご相談に来られた製造業の経営者から、このようなご相談がありました。
売上はここ数年で倍増し、取引先との関係性も良好。客観的に見れば優良企業と言える状況です。しかし、今は特需の影響もあるため、この状況はいつまでも続かないという危機感を持たれていました。
当社が以前支援した企業でも、似た状況がありました。
3割、5割と徐々に取引が増え、気づけば主要取引先の売上は、全体の8割以上を占めるようになっていました。
社長はこう話していました。
「うちの会社は、新規開拓ができるのは私しかいない。このままでは、いずれ会社は倒産する。
仕組みとして“新規開拓ができる人が育つ組織”に変えていかなければいけない。
自分が30年かけてもできなかったことだから、何年かけてもよいので、
なんとか仕組みとして“新規開拓ができる人が育つ体制”を構築してほしい」
という強い要望でした。
短期的な成果追求というより、組織の体質として改善をしていきたいというご依頼でした。
実際に取り組んだことは、強みをベースにした事業戦略の明確化をはじめとして、提案資料やホームページを整え、対面セールスの型をつくり、既存顧客への商談の中でも新しい価値提案を試す。そんな地道な積み重ねを実施していきました。
最初は、戦略づくりからスタートするのですが、毎月の指導を通じて、現場の社員の方にも一緒に考えてもらい、意見を交わしていきます。
そうすることで、当社からの一方通行の伝達ではなく、一人一人が考えて自社の戦略を腹に落とし、行動に繋げることができるようになります。
対面セールスの指導については、営業マン個々の実際の商談内容(会話)を精査して、改善するところまで踏み込みます。
ある意味で商談スキルが丸裸になるため、営業マンからすると、少しストレスになる手法ですが、具体的な改善につながる大きなメリットがあります。
こうした地道な改善を2年ほど継続していきました。
営業マンの具体的な行動としては、既存のお客様を中心に新しい価値提案をしつつ、さらに少しずつ新規開拓にも挑戦することを実践していきました。
回数を重ねる毎に、既存顧客への提案が少しずつ採用されるようになり、さらに新規開拓にも挑戦して、徐々に成果を出せるようになっていきました。
繰り返しやっていくことで、まったく、新規開拓ができなかった営業マンが、一人、また一人と、成果を出せるようになり、チーム全体として、自信をつけていったのです。
このようなことは、他のプロジェクトでもよく見られることで、新規開拓ができなかった人ができるようになる姿を目の当たりにする大きな効果があります。
「あの人ができるなら、自分もできるのではないか」と、再現性に確信をもって、自己の営業スタイルの改善に注力する雰囲気が広がります。
また、比較的若い方のほうが、習得が早いため、キャリアのある先輩社員は、「負けていられない」という感覚で奮起する方も多くいらっしゃいます。
その後、前述した「“新規開拓ができる人が育つ体制”を構築してほしい」とご依頼があった同社に予期せぬ事態が直撃しました。
コロナで、主要取引先の業界が完全に止まってしまったのです。
当然、同業他社の多くが大きく売上を落としました。倒産した企業も多かったと聞きます。
しかし、同社は準備していた強みや営業ツールを武器に、新しい業界へ一気に踏み出しました。営業マン全員が新規開拓に動き、わずか1年で事業売上の半分にあたる5億円の新規売上をつくりました。経営危機を乗り越えたどころか、増収になるという快挙を達成しました。
これは偶然ではありません。
平時の積み上げが、非常時の大きな力に変わったのです。
このような取り組みもレベルを上げていくと、社長だけではなく、現場の社員の方が、次に攻めていく業界を定めて、戦略をつくり、営業を仕掛けていくようなこともできるようになっていきます。
当社のクライアントでも、長年のお付き合いを通じて、そのようなレベルに達している会社が複数存在します。
あなたの会社はいかがでしょうか?
もし、なんらかの理由で、主要顧客の方針が変わり、取引がなくなると分かった場合、立て直す体制をすぐにつくることができるでしょうか?
あるいは、業界全体が停滞した場合、次の一手を準備できているでしょうか?
そういった、目をそむけたくなることに向き合えるのは、現場の社員ではなく、社長しかいません。
もし、以下の項目に、当てはまるようでしたら、注意が必要です。
□ 主要顧客からの発注量が増え続け、比重が高まっている
□ 逆に主要顧客からの発注量が、ここ数年減ってきている
□ 発注量は減っていないが、取引条件の調整や見直しが増えている
□ 利益率が以前よりも下がり、改善しにくい状況が続いている
□ 競合が顧客の周辺領域に入り込み、少しずつ浸食が進んでいる
□ 2〜3年先の需要が減速するという業界予測が出ている
実際には、このような状況にあっても、対策を後回しにし続けてしまう経営者は少なくありません。
逆に、先にご紹介させていただいたような、順調な時に危機感をもって取り組む企業の方が、少数だと思います。だからこそ、そういう会社は、優良企業であり続けるのです。
- 主要顧客への依存度はどれくらいか?
- 次の柱になり得る市場はあるのか?
- そもそも自社の強みは整理されているか?
- 新規開拓に注力できる体制はあるか?
こうした項目を落ち着いて見つめ直すだけでも、次に何をすべきかが明確になります。
主要顧客に頼り切るのではなく、自社で開拓する力を少しずつ育てていくこと。
その積み重ねが、将来の安定へとつながっていきます。
しかし実際には、新しいことに挑戦しなければならないと理解しつつも、現場のことが手一杯で、いま一歩踏み出せない経営者も多いと思います。
そのため、新規事業にいきなり挑戦するようなハードルが高いことからではなく、既存事業を柱としながら、できることから、毎月コツコツと取り組んでいくことが大切です。
その取り組みが、3年後、5年後の成長の支えになります。
地道な積み重ねが会社の未来を大きく変えるのです。
貴社もそろそろ、主要顧客への依存体質を見直しませんか?
追伸:
当社では主要顧客への依存体質を見直そうとされる中小企業を支援しています。
一歩踏み出そうと思われる経営者は、まずは当社のセミナーにご参加ください。
戦略を形にしていく具体的なプロセスについて詳しく解説します。
セミナー詳細 ➡ ヒット商品・カテゴリーキラーのつくりかたセミナー