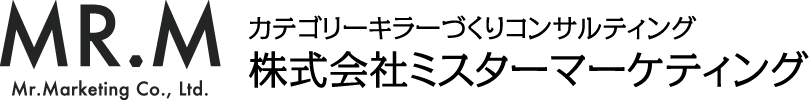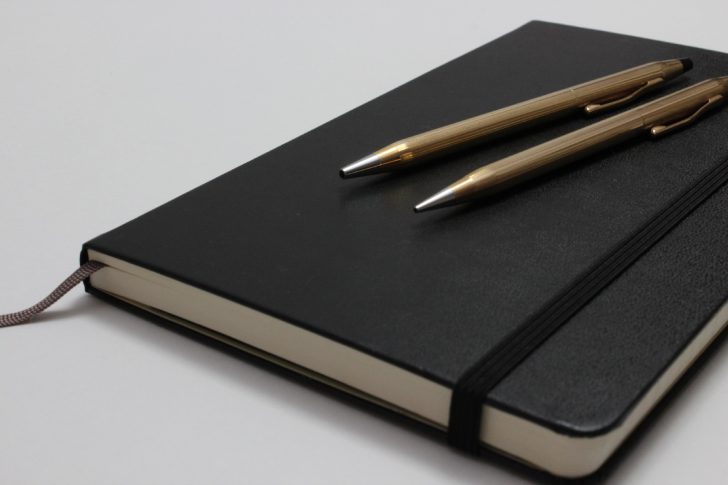第128話 中小製造業経営者のための―成果を出す“マーケティング具体的実践法”
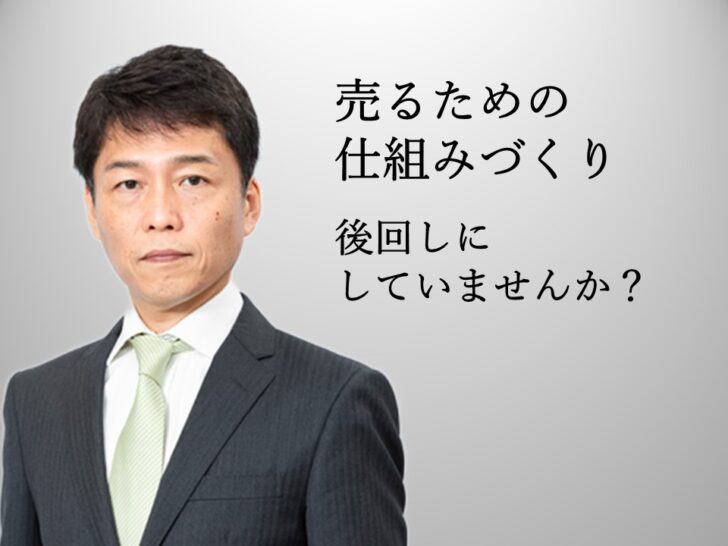
「先生、うちの会社は、それなりに強い商品があるんですが、それがだんだん頭打ちになってきています。
いまのうちに次の売上の柱をつくっていかないと、将来が不安です…」
これは、創業50年以上にわたり日本のものづくりを支えてきた製造業の経営者からいただいたご相談です。
同社には確かな技術と信頼があり、主力商品はこれまで力強く業績を支えてきました。さらに、営業力も高く、これまで自ら市場を切り拓き、実績を築いてこられた会社です。
しかし、その営業の力が大きな強みである一方、体制はやや俗人的になり、新しい商品が思うように市場に広がっていかないという課題に直面されています。
強い自社商品を持っている会社は、比較的高い利益率で経営ができます。
しかし、その状況をいつまでも競合が放っておくことはありません。必ず追随商品が登場し、市場は侵食されていきます。
あるいは市場がある程度、飽和していたり、縮小することで、成長が鈍化していき、思ったより売上が伸びない、または売上が下がってくるフェーズに入っていってしまうこともあります。
だからこそどんな企業も、「次の売上の柱」を常に準備しておくことが欠かせないのです。
これは自社商品を持つ会社だけではありません。実は、受託製造業にも同じことが言えます。
特に受託製造業は、価格競争に巻き込まれやすく、利益が出にくい体質に陥りがちです。
その大きな要因は、「差別化された事業に見えていない」ことにあります。
同業他社のホームページを見ても、『高品質』『短納期』『柔軟対応』といった表現が並ぶことが多く、結果として違いが見えにくくなっています。そのため、本来の強みが十分に伝わらないケースが少なくありません。
柱が一本だけの会社は、その市場が縮小した瞬間に経営が一気に厳しくなります。
さらに、そもそも明確な柱がない会社は、安定した収益の軸を持たないため、常に価格競争にさらされ、慢性的な疲弊を強いられます。
いずれのケースでも必要なのは、差別化戦略を描き、自社ならではの「強い柱」を設計・育成していくことです。
これこそが、経営者に求められる最重要の取り組みです。
大切なことは2つです。
- 顧客ニーズにもとづいて、競合にない有益な差別化商品または事業を生み出すこと
- その商品や事業を、お客様に確実に届ける「売れる仕組み」をつくること
当社では、この「競合他社を圧倒する差別化された強い商品・サービス・事業」を カテゴリーキラーと呼んでいます。
「差別化商品」と聞けば、イメージしやすい方は多いと思います。
たとえば…
- 特殊加工をした便利な雑貨製品
- 独自成分を配合したサプリメント
- 特定のニーズにフォーカスした生活家電
といった“単品の商品”が差別化商品です。
一方で「差別化事業」とは、商品単体ではなく、製造業としての事業全体を「カテゴリーキラー」にすることを意味します。
たとえば…
- 特定業界に特化する事業
「金属素材の加工をやります」ではなく、
「食品製造機器に特化した加工メーカー」として事業を位置づける。
- 特定用途に特化する事業
「段ボールなら何でもつくります」ではなく、
「特殊形状の段ボール」に特化する。
- 掛け合わせで独自領域をつくる事業
「モニター製造」×「コンテンツ提供」を掛け合わせ、
「建設現場の安全対策モニター事業」として独自の市場を切り拓く。
などです。
いずれも、差別化が無い状態から生み出した、当社お客様のカテゴリーキラー例です。
カテゴリーキラーを確立した後には、それを市場に届ける仕組みが必要です。
製造業にお勧めの代表的な仕組みは、次の5つです。
(1)ツールが営業マンになる ― ブランディングツールの整備
ホームページやパンフレットが、ただの紹介資料ではなく「お客様を動かす営業マン」として機能するように設計します。
(2)お客様から吸い寄せられる ― 展示会によるプル型集客
展示会に出展し、単なる名刺交換ではなく「ぜひ話を聞かせてほしい」と言われる状況をつくります。
(3)狙った相手に届く ― プッシュ型のダイレクトアプローチ
ダイレクトメールやテレアポを活用して、ターゲット企業に直接アプローチ。見込客を「待つ」のではなく、計画的に「攻める」仕組みです。
(4)潜在ニーズを引き出す ― 聞き込み型営業
商品説明ではなく、課題を徹底的にヒアリングすることで「まさにこれが欲しかった」と言われる受注を実現します。
(5)将来客を育てる ― フォローアップの仕組み
メルマガやダイレクトメールによる、定期的な情報発信を通じ、すぐには買わない見込客を教育し、数カ月後・数年後の成約へとつなげます。
これらはすべて、当社のコンサルティングで実際に成果をあげている手法です。
実際に、こうした仕組みづくりによって成果を上げている、最新のケースを1つご紹介したいと思います。
ある老舗の産業用機器メーカーは、過去に展示会に出展するも、全く成果出ない状況でした。少しの名刺は集まったのですが、商談まで至るケースはゼロ件でした。
私たちはまず、事業そのものをカテゴリーキラーとして再設計。
さらに、ブランディングツールの刷新(HP・パンフレット)と、展示会での訴求ストーリーや導線設計を徹底的に強化しました。
こうした取り組みを約1年半にわたって進め、その成果を試す場となったのが、今年7月に開催された『ものづくりワールド2025』でした。ここでは、これまで成果につながらなかった展示会が一変し、具体的な商談が次々と動き出す“案件創出の場”となり、大きな成果へとつながりました。
展示会後の反響は目覚ましく、翌月の8月には具体的な案件アポでスケジュールがいっぱいとなり、やむなくお断りしなければならない状況にまでなったのです。
単なる名刺交換にとどまらず、「工場を見学させてほしい」「自社の機械を見てほしい」「ぜひ一緒に進めたい」という引き合いが次々に生まれました。
この成功の詳細については、改めて当社の特別インタビューレポートや、セミナーでもご紹介してまいりたいと思いますが、差別化戦略と“売れる仕組み”の両輪で、同じ展示会でも結果が180度変わることを示す好例です。
ちなみに、同社は、この流れを止めることなく、続いて、別事業部のカテゴリーキラーづくりに挑戦されています。良い流れがでると一息ついてしまう会社も多いですが、流れを止めず、継続して挑戦することは、とても重要です。
ここで紹介した一連の取り組みは、総称すれば「マーケティングの強化」です。
日本の製造業は、技術や品質の向上には熱心ですが、マーケティングを強化しようという意識はまだまだ低いのが実情です。
しかし、当社に相談に来られる経営者の多くは、マーケティングを経営に取り入れる重要性に気づき、実際にこれらの仕組みづくりに挑戦して成果を出されています。
もちろん、成果の差は大小ありますが、改善を積み重ねていくことで、確実に良くなっていきます。
問題は、このような仕組みづくりに挑戦しないことであり、また途中で手を止めてしまうことです。それは、製造業が技術や品質の強化の取り組みを止めてしまうことと同じです。
製造業の技術進化と同じように、マーケティングも進化していきますので、コツコツと改善、進化を繰り返していく必要があります。
それが、次の5年、10年、20年の安定成長を切り拓く道につながります。
日本は、しばしば世界から「技術で勝って、事業で負ける」と評されています。
この状況を打開するために、今こそ製造業は マーケティングの強化に力を入れるべきです。
まじめにものづくりに取り組む会社こそ、本来は報われる存在であり、これからの日本をさらに強くしていく重要な存在です。
だからこそ、1社でも多くの製造業経営者がマーケティングの必要性に目覚め、成果を手にしていただきたい――それが私たちの願いです。
追伸:
今月より、製造業にフォーカスしたセミナーを開催します。まだ、当社の「カテゴリーキラーの作り方」セミナーにご参加されたことがない、製造業の経営者はぜひご参加くだい。様々な製造業の事例と考え方を解説する予定です。これからの自社の戦略について、じっくり考える時間にしていただきたいと思います。
- 中小製造業のための価格競争を脱却して独自市場をつくる
カテゴリーキラーの作り方セミナー
https://www.mr-m.co.jp/lp/
株式会社ミスターマーケティング
代表コンサルタント
村松 勝